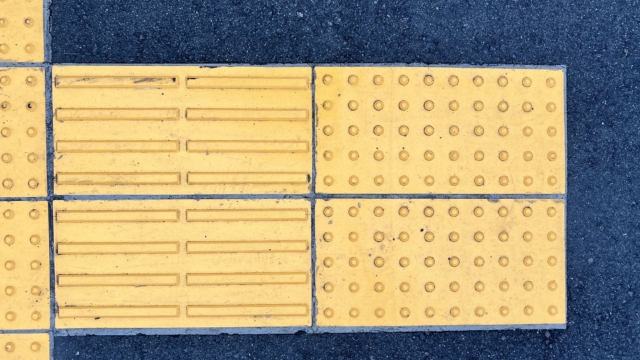日々を暮らしていくために考えておきたいことはたくさんあります。今日の昼ご飯を何にしようかと迷うことはしょっちゅうですし、職場や学校でどう振る舞うべきかも悩みどころです。そろそろ髪を切りたいな。あのマンガの新刊が出るらしい。こないだの舞台おもしろかったな。脳はひっきりなしにたくさんのことを考えていて、世界と自分との関係をアップデートし続けています。
ところが、自分の体調に関する悩みがあると、思考リソースの多くはそちらにごっそり割かれてしまいます。病気やケガのことで頭がいっぱいになり、ほかのことを考える余裕がなくなります。
そして、私たちの思考は、徐々に体調不良の「原因」に向かっていきます。
「いやいや、私は別に病気の原因なんかわからなくていい、知りたいとも思わない、とにかく早く治してくれればそれでいい」なんておっしゃる方もいらっしゃいます。学者じゃないんだから、メカニズムなんて興味ないよ、と。
でも、それは、痛みや苦しみと付き合う時間がまだ短いときの話です。長期にわたって辛さを抱えている人は、必ず、「なぜこの痛みが出るのか」「なぜ私がこのような目に合わなければいけないのか」と、”why”を考えるようになります。
人間は「なぜ」を問わずに長時間悩むことができない生き物です。つい無意識に、悩みの根っこを探りにいってしまうのです。
ところが、前回ここでお話しさせていただいたように、病気というのは必ずしも原因が明確なものばかりではありません。そのため、”why”思考は終わらない迷路に迷い込んでしまいます。
「原因不明」はありふれている
たとえば私たちは、どうして五十肩になるのでしょうか。肩関節が加齢によって痛むから、という、一見明確な原因が知られています。けれども、世の中には、五十肩になりやすい人となりにくい人というのがいますよね。同じような生活をしていても、頻繁に肩が痛む人とまるで平気な人に分かれるというのは不思議ではありませんか。「なぜこの私が五十肩になり、同期のアイツはならないのだろう」まで質問を掘り下げると、「原因の一部は不明」と言わざるを得ません。
「胃の中にピロリ菌がいて、胃潰瘍になった」というケースでは、「胃潰瘍の原因はピロリ菌」と言えそうです。実際にそのように書いてあるウェブ記事なども目にします。たしかに、ピロリ菌の初感染で激烈な症状を呈するお子さんはいらっしゃいます。でも一方で、長年ピロリ菌が胃の中にいたのにほぼ無症状のまま天寿を全うする人というのもいらっしゃいます。つまり、ピロリ菌だけが「病脳」(病気で悩むこと)の単独の原因とは言えないわけです。免疫や、胃酸の分泌度合いなどが複雑にからみあって、結果として胃潰瘍になったり、ならなかったりします。ちなみに、ピロリ菌以外の理由、たとえばNSAIDsのような薬の副作用で胃潰瘍になることもあるので、「胃潰瘍の原因はピロリ菌」という表現はいくつもの意味で不正確です。
がんはどうでしょうか。国立がん研究センターのがん情報サービス(https://ganjoho.jp/public/knowledge/basic/index.html閲覧日:2025年6月19日)を見ると、「がんは遺伝子が傷つくことによって起こる」と書かれています。これが原因と考えていいでしょうか? でも今度は、「なぜ遺伝子が傷つくのか」が気になりますよね。
先の記事をより細かく読みますと、「日本人を対象とした研究では、喫煙、過度の飲酒、塩分や塩辛い食品を取りすぎる、野菜や果物をとらない、熱すぎる飲み物や食べ物をとるなどの食生活、太り過ぎ、痩せすぎ、運動不足、ウイルスや細菌への感染ががんの要因になる」と書かれています。急に情報量が爆発しましたね。これらが全て原因ということでしょうか? よく読むと、原因とは書かれておらず、要因という言葉が用いられています。遺伝子に傷がつく過程では、複合的なファクターが関与し、どれが原因であると確定しづらいので、要因と表現しているのです。
こうして、ひとつひとつの病気を考えていくと、どうも「原因」がはっきりしている病気のほうが少ないんじゃないかという気持ちになってきます。
「ケガだったら、原因がはっきりしているじゃないか」と思われた方もいるかもしれません。でも、それも誤解です。受傷機転がわかっていたとしても、その回復過程にたくさんの要因が関与するからです。細胞の代謝速度、血流、常在菌の存在などによって、似たような傷でもたどる道のりは千差万別です。「この切り傷の治りが遅い原因はなにか」となると、ぐっと難しくなります。
結局、人体に関する”why”には、たいてい、答えがないんです。仮にあっても複雑過ぎて、理解できるレベルではなかったりするんですね。
原因不明との「向き合い方」は?
たまに質問を受けます。
「原因不明の病気がたくさんあるというのはわかった。けれども、それなら、原因不明の病気と長く付き合わなければいけない私の不安は、どのように解消したらよいのだろうか。原因不明との向き合い方みたいなものを教えてほしい」
そうですよね。
原因不明と聞くと私たちは不安になります。これは、理屈というよりも本能からくるものです。
私たちの脳は、「メカニズムがわからず根っこが抑えられないものを見ると不安になるようにできている」のですね。原因を除去することで状況をよい方向に進めて生き残ってきた、そういう進化の果てに私たちが今こうして暮らしています。
暗闇でがさごそと音がして、細長いものが出てきたときに、「それが何なのか」を確定しないままのんびり過ごしていると、毒蛇だったときに噛まれて死んでしまいます。だから私たちは、「なぜ暗闇で音がしたのだろう」という原因を探り当てるまで、ドキドキと胸のざわめきが止まらず、元にあるものを究明するまで落ち着かないような本能を身につけました。
しかし、この「究明グセ」が、ヘビとか蚊とか猛禽類とか猛獣に及んでいるうちはよかったのですが、病気という複雑系の権化みたいなものにまで及ぶと、あまりよろしくないのです。「考えても解決につながらない不安を抱え続ける」ことになってしまうからです。
身も蓋もないことを言えば、「原因不明の病気という不安と向き合う」ということ自体が、「負け確」(負けが確定した状態)なのだと思います。
本能からの、ちょっとした脱出
人間は本能的に、whyを駆動させがちです。不明なままのものを残しておかないために、常に原因を探ろうとするクセがあり、その間はずっと不安なままでいるのです。
前回の記事にちょっと書いたのですが、じつは現代の医学は、「原因が不明であっても治療はできる」という方針を強化しています。根っこを叩いて病気を直そうと思っても、根っこが複数あって叩ききれないので、代わりに原因がどうであっても治療できるような薬が次々と開発されています。
つまり、病気を治したり、うまく付き合ったりする上で、「原因は不明なままでよい」ということです。いいですか? 原因なんて不明でいいんですよ。
それでも、私たちは心のどこかで、治療とは関係ないレイヤーで、「原因不明だと不安だなあ」という気持ちを捨てきれないでいる。これはある種のバグだと思います。このバグに、どう対処したらよいでしょうか。
いくつかのやり方はあると思うのですが、ひとつの提案としては、マインドフルネスの手法を取り入れてはどうか、ということです。マインドフルネス、ご存知ですか? ヨガとか瞑想とかとも似ていて、印象はけっこうスピリチュアルなので、うさんくさいと思っている方もいるとは思いますが、概念としてはそれほど奇妙なものではありません。
体験を体験のまま受け入れて、原因探りとか評価とか判断をせずに、「今これがこうなっているのかあ」ということに一つ一つ集中していくということです。このとき、痛みだけに一点集中するのではなく、体や心のすべての領域を丹念になぞっていくことがポイントです。できていること、できないことを、価値判断とは別に確認します。自分の体を、ここには痛みがあるな、こっちには痛みを感じないしわりと元気そうだな、こっちは休み休みなら使えそうだな、といったように、いい・悪いや、「なぜ」を探らないまま、粛々とチェックして受け入れていく。
「原因」なんてわからなくても対処はできます。自分を悩ませているものの「理由」が知りたいのは欲求として当然ですが、そんな古い本能に振り回される必要なんてありません。
私たち人間は、かつてサバンナにいたときの本能で、過剰に”why”にとらわれています。そんな本能からは脱出したらいいんじゃないかと思うんですよね。
答えのない”why”を考えるのがしんどくなったら、”what”とか”where”とか”how”とかを実直に探っていったほうが、気持ちが楽になります。本能に振り回されず、本能をかるくあしらうくらいの気分で、うまくやり過ごすことができればいいですよね。