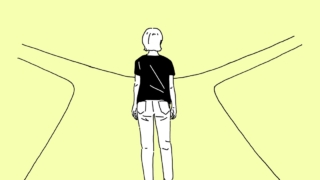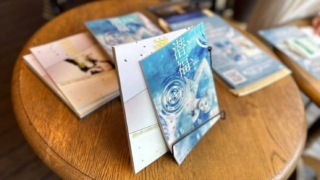人には、各々の考えや気持ちがある。たとえ、家族であっても心を縛るのはタブー。そう感じるのは、私自身が「自分の声」を取り戻すのに試行錯誤したからだ。
「私の言う通りにしていれば間違いないから」と自分の理想像を押し付ける過干渉な母と、罵声で家族を押さえつけるモラハラな父。争わずに生き延びるため、私は言いたいことにブレーキをかけるのが癖になった。
その結果、私は複雑性PTSDと診断され、今もカウンセリングに通っている。今回は、自分の意志が言えなくなると、心はどう壊れていき、回復には何が必要になるのかを語りたい。
家族の中で「唯一の聞き役」だった
私の家族は、各々が言いたいことを話す。私は、いつも聞き役。嫌なムードになった時にはあえて馬鹿なことをして雰囲気を変えるピエロでもあった。平和な時間を少しでも持続させるには、それしかなかったからだ。
たまに、自分の考えを母に伝えることはあったが、決まって「こっちのほうがいい」と却下された。いつ、どんな言葉が怒りの引き金になるか分からない父には自分の気持ちなど、言えたことがない。
それでも、小学校低学年までは母から「口から生まれた子」と言われるほどのお喋りだった。きっと幼いながら、伝えたい気持ちを必死に言語化していたのだろう。
だが、感情や意思を尊重してもらえない経験が増えていくと、人は絶望し、諦める。いつしか、私は全く自分の気持ちや考えを話さない人間になっていた。
何を考えているか、よく分からない子。母からよく、そう言われていたが、そうした言葉に反論したい気持ちすら湧かなくなっていた。
家庭内で学んだコミュニケーション法は、その人にとっての「基準」になる。私は友人と話す時も、いつも聞き役だった。
自分の近況は序盤に、ほんの少し話す程度。あとは延々と、友人の話を聞く。それが、自分にとっては楽な人間関係だと思っていた。
彼氏から「どうしたい?」と聞かれて困惑
その考えが変化したきっかけは、今の夫と出会ったことだった。
夫は、それまで付き合った男性たちとは違い、何をするにも私との対話を望んだ。ご飯を食べるお店を決めるだけでも、「諭香はどうしたい?」と聞かれ、返答に困った。
次回のデートを決める際にも「どこか行きたいところはある?」と尋ねられ、困惑。「あなたはどうしたい?」の問いを投げかけられると、頭が混乱することに気づいた。
当時の私は、食べたいものや行きたいところなど思いつかなかったし、自分の提案を相手がどう捉えるかが怖かった。だから、いつも「私は本当になんでもいいから決めていいよ」と答えるのが精いっぱいだった。
それでも夫は毎回、何かを決める時は必ず私の意見を聞いてきた。「どんなことでも、ちゃんと対話をして決めたいから」と言って。
だからある日、「このカフェ、入りたい」と、本当はそれほど行きたくないお店を提案してみた。本当に行きたい場所など思いつかなかったし、提案後に却下されても傷つかないよう、自分の心を守ったのだ。
すると、夫は「いいね!」と言い、帰り際に「珍しく、行きたいところを聞けて嬉しかった」と笑ってくれた。
本音ではないけど、自分の意見が言えた。私の気持ちを受け入れてくれる人もいるんだ…。人の意見に従ってばかりだった私には、衝撃的な体験だった。
発言時に「動悸」と「息苦しさ」がするようになって
夫と対話を重ねる中で、私は少しずつ自分の感情が分かるようになり、言えるようにもなっていった。興味を惹かれる場所はないかと、自ら積極的に調べるようになり、「世界はまだまだ広い…」と驚きもした。
だが、自分の意見を伝えられる相手ができたことで、新たな悩みが…。聞き役に徹してきた時間が長かったからか、自分の意見を伝えようとしても上手く言葉が出てこなかった。気持ちは溢れだすのに、頭と口がついていかないのだ。
また、ライターという職業も自分の中で重荷になった。話す時も書き言葉のように分かりやすくしなければ…と、余計なプレッシャーを自分に課してしまったのだ。
やがて、私は取材時や打ち合わせの時など、夫以外の人と会話する場面で動悸がするように…。話している最中には息苦しくなり、「呼吸ができなくなる!」と恐怖を感じた。
実は、このサイトを運営する「NPO法人こんぺいとう企画」が行ったクラウドファンディング中のYouTubeライブ時にも、この症状は現れていた。
会話時の動悸と息苦しさに苦しんでいたピークの時期だったが、なんとか笑顔を作って乗り切ったことを覚えている。
こんな症状が続くのなら、取材ライターはもう無理かもしれない。本気でそう悩んだ時期だった。
2年間の対話練習を経て「自分の声」を取り戻した
だが、カウンセリングを通して、私は徐々に、この症状が出る原因に気づいていった。私の場合は自分の意見を言語化し慣れていないことや自分の気持ちを受け入れてもらえた経験が少なかったことだけでなく、人間に対する恐怖心が強かったことも大きく関係していたように思う。
ただ街を歩いているだけでも、私は人が怖かった。コンビニやスーパーで「支払いはPayPayで」と店員さんに伝えることさえも怖かった。周りの人すべてに、自分の声を拒絶される気がして。
そんな周囲への不信感や恐怖心を和らげてくれたのは、カウンセラーと夫だった。カウンセラーは私を肯定しながら、恐怖心を受け止めてくれた。
家庭環境を踏まえた上で、「その恐怖心はあって当然」と寄り添いつつ、自分にはない角度からのアドバイスをくれたから、私は恐怖心への向き合い方が変わったように思う。
夫はマメに私を気遣い、意見を言いやすい関係性を保ってくれた。意見が食い違った時も、「僕は○○だけど、そういう考え方もあるよね」と私の気持ちも尊重してくれ、安心できた。
そうした生活を2年ほど続けて、ようやく私は「自分の意見を受け止めてくれる人もいるんだ」と思えるようになった。そして、自分が「わがまま」だと思っていた意思表示は一般的に見れば、”ごく普通なもの”であることにも気づいた。
正直、今もまだ取材中や会話時に息苦しくなることはある。だが、もう自分を責めはしない。「それだけ一生懸命やってるってことだね」と自分を労わる方向へ心の舵を切るようにしている。
また、「どうせ、上手く言葉にできないんだから、気持ちだけは伝わるように話そう」という開き直りのような考え方は自分にとって大きな救いとなった。「下手くそな言葉でいいや」と、ありのままの自分をさらけ出すことが私にとっては大事だったようだ。
不思議なもので、そういう話し方をするようになると、私の思考自体に興味を持ってくれる人との出会いが増え、クライアントと深く繋がりながら仕事ができるようにもなった。
自分の意見を伝えることは、大切な自己開示のひとつ。虐げられ、なかったことにされた声を取り戻すのには時間も根気も必要だが、覚悟を決めて挑戦してみる価値はある。それは、置き去りにした”あの日の自分”を救うことにも繋がると思うから。
生まれ落ちた家庭で当たり前だったコミュニケーション法を断ち切ることは難しい。だが、私は両親のように、意見が異なる相手に対して無視や拒絶というコミュニケーションしか取れない人間でありたくない。
自分にしっくりくるのは、夫のように「そういう考えもあるね」と相手の考えを認めた上で、自分の考えや想いも伝える対話法だと気づいたからだ。
だから、今は夫を相手にして、相手と意見が食い違った時の対話法を密かに練習している。ようやく取り戻せた声は尊いからこそ、これからは自分で守りながら、必要な場面でちゃんと発することができるように、ゆっくり育てていきたい。
全ての人に受け入れられなくても、身近な人から拒絶された経験があっても、自分の意思や感情に価値がないなんて思わないでほしい。もし、2年前の私と似た思いをしている人がいたら、日常の些細な場面から「私が今、したいことは?」と、時間をかけて自問自答してみてほしい。