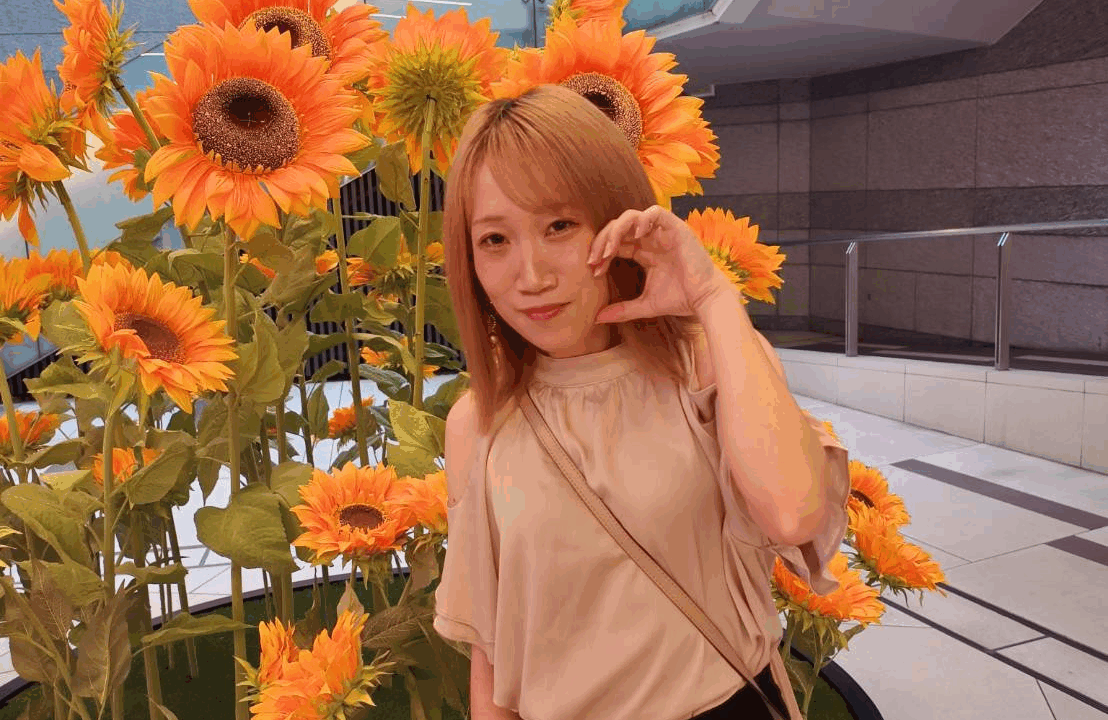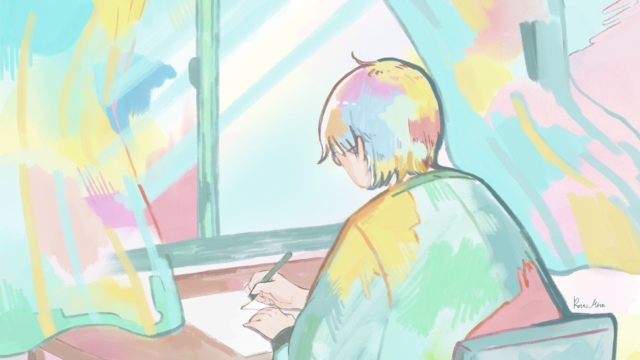人が持つ感情には、どれも価値があるという。だが、私は自分の「怒り」が許せなかった。父の理不尽な怒りは幼心を傷つけ、過干渉な母の怒りは私の生き方を狭めた。私にとって怒りは、備わっている意味が分からない感情だったのだ。
だが、2年半ほど前に複雑性PTSD(※長期にわたる虐待やDVなどにより起きる精神疾患)と診断され、カウンセリングを通して怒りに対する考え方や傷ついた日々を思い出す中で、少しずつ”怒りの受け止め方”が変わっていった。
「怒り」は悪い感情と思い続けてきた
怒りにまつわる記憶には、いい思い出がない。それはきっと、私だけではないはずだ。怒りは自分に向いても、誰かに向けてもいいことが起きない。人間関係のいざこざが起きるのも、怒りという感情があるせいだ。
そんな煩わしい感情が備わっていなければ、人はもっと平和に関わり合っていけるのに。私はずっと、そう思っていた。
怒りは二次感情だといわれている。悲しさや寂しさなど、他の一次感情が満たされなかった場合、怒りという感情が顔を出すのだ。
だったら、自分の中で未消化になっている悲しみや寂しさを癒してあげれば、私は心の中で必死に押し殺している「怒り」という感情に振り回されず、心穏やかに生きていけるのではないだろうか。そう思い、複雑性PTSDと診断されてからは、カウンセリングを受けて傷ついた心の修復に励んだ。
それなのに、傷つけられた自分と向き合うたび、怒りの感情は強くなっていった。心は満たされるどころか、暴風が吹き荒れているかのような在り様。
持っていては苦しいこの悪い感情を、なんとかして手放したい。そう思い、カウンセリングに通い続ける日々は正直、地獄だった。
「怒り」は自分を守る盾だと気づいて…
カウンセリングを続けるほど、私の怒りは表に出やすくなった。いつもなら家族からトゲのある言葉を言われても、「もともと、こういう考え方をする人たちだから…」と流せたり、「人はみんな脳の構造が違って凸凹があるから仕方ない」と自分を納得させたりできていたのに、それができず、激しい苛立ちを抱くようになった。
そして、赤の他人にも怒りを抱くように。例えば、レジで横入りされた時や自分を軽く見られていると感じた言動をされた時。なぜ、私がこんな扱いをされなければならないのか。どうして、私だけが我慢してやり過ごさなければならないのか。
そんな考えが自然と心や頭に浮かんでくるようになり、ハっと気づいた。もしかしたら、怒りって自分を守るために働いてくれる感情なのかもしれない、と。
怒りを嫌っていた私は、自分に優しくなかった。人前では、親切ないい子。でも、自分の扱われ方には無関心。「考え方は人それぞれ違うから」と気持ちをなだめ、感じた怒りをなかったことにするのが当たり前の日々だった。
実際、メンタルクリニックで受けた心理検査でも、私は怒りを他人や自分にぶつけることなく、「なかったもの」として処理し、対処法を探すという心のクセがあると診断された。なかったことにできない激しい怒りなんて、これまでにいくつもあったはずなのに。
私は感じた憤りを「なかったこと」にし、誰も傷つかない対策法をひとりで探してきたから心が壊れ、カウンセリングで怒りの学び直しをすることになったのだ。
そんな心のクセに気づくと、怒りに対する感情が少しずつ変わっていった。怒りは、自分が不当な扱いを受けた時には出していいものであり、出すべきものである。怒りという感情が備わっているからこそ、人は自分や大切な人・ものを守ることができると思えるようになった。あれほど忌み嫌っていた感情が、実はとても大切なものだったと知った時、泣けて仕方なかった。
これまでの私はどれほど無防備な状態で、周囲の雑な扱いも笑って受け止め、必死に生きてきたのだろう…。切なくなったから、その時、私はこれまで傷ついてきた自分に約束をした。「これからは私が私を守る。もう誰にも傷つけさせないよ」と。
「怒り」の表現は”自分の意志”を伝える第一歩にもなる
怒りは持っていい感情。そう認められるようになると、自分の言動にも変化が見られた。例えば、家族との向き合い方。「あんたは女らしくない」「いつもメイク用品が汚い(笑)」など、ややトゲのある言葉をぶつけられた時、流すことなく、「そういう言葉は私が傷つくから止めて」と言えるようになった。
怒りを出すことに慣れていないから、手は震えるし、発する時には心臓がドキドキする。だが、「もう私だけが傷つく人間関係は築かない」と自分自身と約束したから、躊躇っても言葉に出す。
怒りは、たしかに扱い方が難しい感情だ。TPOを考えずに出せば相手を傷つけるし、理不尽な怒りは円滑な人間関係の形成を阻む。だが、適切に発動させることができれば、自分を守る”最強の盾”になる。
しかも、盾として活かせば不思議なことに、周囲の態度も変わっていく。明らかに上下があった関係性の形が変わり、相手から発せられる言葉が少し丸くなった。「何か言うと、言い返してきてめんどくさいヤツ――。」もしかしたら、家族からはそう思われているのかもしれないが、それならそれでいい。自分の一番の目的は、”怒りを適切な時にちゃんと発動させて自分を守ること”だから。
ちなみに、怒りを伝えられるようになると、逆に怒りがこみ上げてくる機会が減るという不思議な現象も起きた。
怒りを伝えるということは、いわば、自分の意志を相手に伝えるということ。だから、一方的に相手に怒るのではなく「私は○○という理由から△△だと思うんだけど、あなたはどう?」と、自分から話し合いのきっかけを作れるようにもなった。
”いい子”を演じる中で秘めてきた「怒り」には価値がある
これは持論なのだが、私のように親の顔色や家の雰囲気を読み取りながら暮らしてきた元子どもは人と話し合う機会が圧倒的に少なく、人間関係を育む時に苦悩している印象を受ける。
話し合いの仕方を家庭で学べなかったから、穏やかな方法で毅然と人に自分の意見を伝える方法が分からない。そして、慎重に予想した親の心中は的中していたことが多かったため、家族以外の相手の気持ちも自分が想像している通りだと思ってしまう傾向もあると思う。
実際、私はそうだった。うちの親は機嫌が悪いと、口数が減るタイプ。だから、結婚後、夫が普段よりも無口だと、「不機嫌なのでは…」とビクビクした。
だが、話し合いができるようになって知ったのは、予想の的中率の低さ。無口の理由は、単に眠かっただけとか疲れていたとか、私に対する感情とは全く関係がないことだった。そうした事実をフランクな話し合いという形で何度も確認していくと、同じ状況に遭遇した時、不安に駆られにくくなった。
長年、いい人や優等生として生きてきた人にとって、怒りを表に出すのは文字通り、死ぬほど怖いことだろう。しかし、その勇敢な選択をした後にはきっと、今よりも息がしやすい世界に出会えると思う。
少しずつでいい。これまで誰かを守り、支えてきた人は「自分を最優先に守っていい」という赦しを自分に与え、押さえつけてきた怒りを愛してあげてほしい。