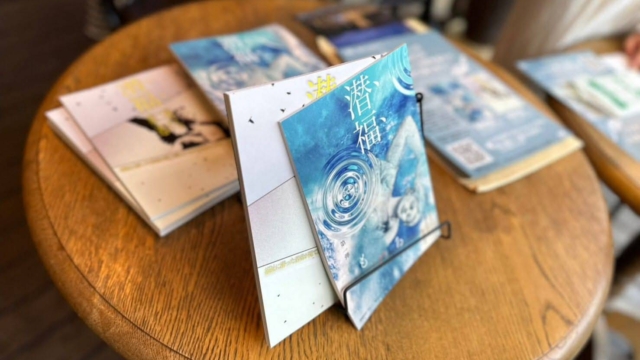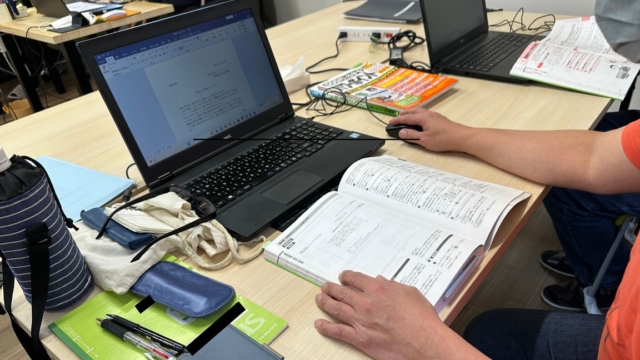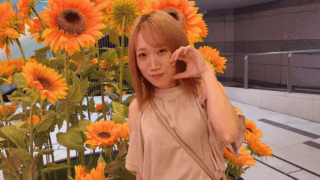福祉現場で欠かせない「記録」
「まず最初に聞きますが、『記録』は誰のためのものですか?」
ある支援記録に関する研修で、研修の冒頭、講師から投げかけられた質問だ。会場がざわざわとする中で、講師がぴしゃりといった。
「あなた以外の誰か、のためのものです。」
支援記録とは、利用者の日々の健康状態や行動、気分の変化、加えて提供した支援の内容を記録するものだ。本人の生活状況を正しく理解し、スタッフ間での情報共有・認識統一を図ることで、はじめてチームとして一貫した支援が行える。
チームとしての支援の質を高めるうえで、記録が的確に取られ、共有される重要性は、現場に身を置いた人なら誰しも頷くだろう。僕自身、働いていた施設での紙ベースでの記録がもどかしく、スマホの記録ソフトへの変更を提案したくらいだ。
記録は、利用者に対してきちんと支援を行った証拠となるし、事故や苦情があった際の検証材料にもなる。だからこそ、事実に基づいて客観的に記述されるべきものだ。そう、あの研修講師が言っていたように「自分以外の誰か」が読んだときに、誤解や解釈のズレがあってはいけないのだ。無論、支援者自身の日記や備忘録であってもいけない。
これは、記録以外の、プロフィールシート、支援記録、アセスメントシート等、福祉現場に散らばるその他多くの言葉たちにも当てはまる。
一人称の言葉を編む
一方で、現場に身を置いている一人として、現場にはこんなにも言葉があふれているのに、何か語るべきことを語れていない、語る場が少ない、そういう感覚があった。
淡々と進む支援現場の中で、生身の人間同士の関わりの中で自分の中に湧き上がる感動や驚きや戸惑いが、言葉にならないまま、お腹の中に沈殿していく感じ。何か大事なものを取りこぼしている感。
その感覚は、福祉の現場に足を踏み入れた他の同世代の中にも、確かにあった。そんな背景もあって、冊子『潜福』を作るとき、「一人称で語ること」がキーコンセプトとなった。
自分が出会った人、体験したこと、感じたことを、自分の言葉で書く。客観的にではなく、主観的に。教科書的な支援論とは距離を置きながら、自分の言葉遣いを大事にする。それらは記録には載ることのない「自分のための言葉」とも言えるかもしれない。
結果として、いくつもの現場から、一人称の言葉たちが集まった。
例えば、特別養護老人ホームの現場での話。ある半身まひの高齢女性によって繰り返されるナースコールに、支援者としての焦りと不安でいっぱいになっていた矢先、自販機の前でふと、その女性から労りの言葉をかけられるエピソード。そこから自分の感情に気付き、ケアの仕事の本質を見出す。(『潜福』第一弾”もぐる”収録「なぜ私が酸欠になったのか」)
他にも、支援対象者である脳卒中による重度の記憶障害のある男性と、野球観戦に行く話。今は離れて暮らす息子が甲子園の予選に出ていることを知り、様々な調整のうえ、試合観戦に一緒に訪れるのだ。敗戦を告げる球場のサイレンのなか、息子を見つめる男性の表情と、改めて支援者としての覚悟を噛みしめる。(”潜福』第三弾”おどる”収録「忘れない」)
どれも記録に書かれることのない、もしくは書かれたとしても、数行の客観的な描写に終わってしまうエピソードたちだ。
「制度」の外で生まれる景色を
また福祉やケアの意味や価値をより多角的に映し出すために、職業としての「支援者」に書き手を限定せずに、福祉サービスを利用する側にいるような当事者や、明確な肩書を持たない学生などからも広く原稿を寄せてもらっている。
例えば、車いすユーザーの難病当事者と友人、そして介助者を交えた3人で江ノ島を訪れた際の記録。いってしまえば、ただの旅行記。そこに、友人との旅行に介助者が同席する絶妙な空気感や、旅行先で出くわす社会的障壁や嬉しい発見が、リズミカルに綴られる。(『潜福』第三弾”おどる”収録「ユイとカナコの江ノ島旅行」)
また、発達障害を抱え、「白黒つけたい」「どっちかに決めたい」性格でありながらも、実家で暮らす母に対しての「好き」であり「嫌い」というアンビバレントな感情に気付く数日間の帰省を描いたエッセイなんかもある。(『潜福』第四弾”はこぶ”収録「グラデーション」)
どちらも、制度に基づいて運営されるいわゆる「福祉現場」の範囲を飛び越えて、日常を起点に、自分と異なる他人とともに過ごすこと、生きることについて自由に考えている。
こうした一人称でかつ業務や制度の外にはみ出していく言葉たちが、時に福祉・介護の世界に向けられる「大変な仕事なのにえらい」「優しい人にしかできない仕事」といったまなざしを軽々と覆し、福祉やケアといったもののリアリティを立体的に浮かび上がらせる力を持っていることは、冊子を発行してきた中で僕ら自身が実感してきたことだ。
誰かと繋がる港を作る
潜福の活動の主軸は冊子「潜福」の発行だが、冊子を出して終わり、ではなく、冊子を媒介に、新しい出会いや繋がりが生まれるようなプラットフォーム=港のような存在になれたら、とも考えていた。
だからこそ、毎回冊子を発行した際にはイベントを実施している。初回、コロナ禍の2021年に開催された第1弾「もぐる」のオンライン出版記念イベントは、哲学者の永井玲衣さんがゲストだったが、200名近くの参加者が集った。それだけ多くの人が、福祉/ケアを語る言葉を、語れる場を探していたということだ。
その後も、新刊を出すたびにゲストを呼んでトークイベントを開催してきた。各回のゲストは文化人類学者の磯野真穂さん、歌人の伊藤紺さん、映画監督の佐々木誠さんと、福祉/ケアの業界ど真ん中から少しずらした人選だ。福祉業界の外にいる、それぞれに尖った専門領域を持つ人を招いてこそ、福祉/ケアを語る新しい言葉や切り口が生まれるのではないか、という期待がある。
当日のイベントには、色々な人が集う。執筆メンバーの知り合いもいれば、ゲストのファン、SNSで潜福を知った人、潜福のことは知らなかったけどイベントが面白そうだから来たという人。
ゲストのトークの後には毎回、アルコール片手の交流タイムも設ける。その場で初めてあった人同士が、潜福を間に挟みながら、楽しく話し出しているのを見るのは嬉しい。そんなことを4年ほど続けてきた。一人称の言葉を起点に、誰かと繋がる港を作る。そんな活動当初のぼんやりとした願いが少しずつ形になっていると感じる、今日この頃だ。
===
文責:御代田太一
1994年、横浜市生まれ。大学時代に障害・福祉の分野に関心を抱き、新卒で社会福祉法人に就職。ホームレスや刑務所出所者を受け止める救護施設にて従事。現在は東京に身を置きながら、2021年より福祉従事者で作るZINE『潜福(せんぷく)』の発行に携わる。