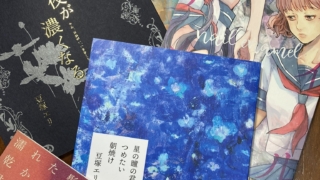「大人になったら二重まぶたに整形しなさい」
小学生だった私に向けて、母がたびたび口にしていた言葉だ。一重まぶたの何が悪いのかはよくわからなかったが、母が私の姿に不満を抱いていることだけは感じ取ることができた。母の何気ない一言が、自分でも気づかないうちに、自己肯定感を蝕んでいった。娘の「幸せ」を願う母なりの愛情からくる言葉だったのだろうとは思うが、些細な言葉の数々が、図らずも、のちの私の人生に複雑な影響を与えることになった。
美しくなければ価値がない
幼稚園生だったある日、宿題が出た。「将来の夢」に関するもので、当人に代わって親が代筆する形式のものだった。私は将来の夢として「かんごふさん」と書いてほしい、と母に言った。しかし翌日、母が渡してくれたノートには、「かんごふさん」という言葉の前に「びじんの」という4文字が付け加えられていた。
当時の私は「びじん」という言葉の意味をよく理解していなかった。後になってそのことを思い出したとき、背筋が寒くなった。
そして小学校に上がる頃には、冒頭の「整形」の話が折に触れて語られるようになった。
幼稚園の頃から中学卒業まで、学校外のテニスクラブに通っていた。テニスコートは屋外で、もともと日焼けしやすい体質なこともあり、当時の私は年がら年中真っ黒に日焼けしていた。
そんな私に、母はいちごやみかんを必死に食べさせた。果物、特に柑橘類があまり好きでなかった私が嫌がると、必ず「色白は七難隠すのよ。ビタミンCをとらなくちゃ」と言った。要するに「あなたの容姿には七難あるのよ」という意味だと、薄々感じていた。今でも柑橘類を見ると、暗澹たる気持ちになる。
絶望の瞬間—「賢さ」よりも「嫁入り」
私は長いこと、母から何を求められているのかを明確に理解していなかった。真面目に勉強し、良い成績を取ることが、評価につながると思っていた。それなりに偏差値の高い大学に合格し、文学部で自分がずっとやってみたかった分野の研究に熱中した。
私とは分野こそ違うが、別の大学で文学部に入った兄が、大学院に進学していた。裕福な家庭ではないということは理解していたが、私ももっと学びたいと思い、院進学について母に電話で相談した。
母は強く反対した。
「大学院なんて行ったら嫁の貰い手がなくなる」と。
その瞬間、私の中で何かが崩れ落ちた。母が私に求めていたのは「賢さ」ではなく「嫁に行くための美しさや愛嬌」だったのだと、その時やっと理解した。幼い頃から母に言われてきた言葉が、すべて1本の線につながった。
これまで私が積み重ねてきた努力や成果は、母にとって価値のないものだったのだと知った絶望は、言葉では表現しきれないほど深いものだった。
私の容姿は母にとっては満足いくものではなかったのかもしれないが、それでも母は決して私を疎んじてはいなかったと思う。むしろ私を大切に思っていたからこそ、幸せになってほしい一心で出た言葉ばかりだったのだろう。
しかしその愛情は、当時の社会が女性に求めていた「女性は美しく愛嬌があり、良い結婚をすることが幸せ」という価値観に強く影響されていた。母自身も、そうした価値観の中で生きてきて、それが「女の幸せ」だと信じて疑わなかったのだろう。
彼女なりに、私の幸せを願っていたことはよく理解している。ただ、その「幸せ」の定義は、私にとっては、あまりにも狭く限定的だった。
残念ながら、当時の私は、母の価値観を理解することができなかった。美しさや愛嬌で女性の価値が決まるという考え方も、女の人生の目標が結婚に集約されるという発想も、どうしても受け入れられなかった。
距離を置くという選択
大学院進学の件をきっかけに、私は母との関係を見直すようになった。電話の頻度を減らし、実家にもあまり帰らなくなった。
たまの帰省や電話の折に、母はしばしば私の外見や、結婚・出産について言及した。そのたびに私は沈黙を貫き、早めに電話を切った。急激な態度の変化に母は当惑したかもしれないが、自分を守るためには必要な選択だった。
外見に関する母の声は、今でも時々心の奥から聞こえてくる。30歳を過ぎて子どものいない私は恥ずべき存在なのではないかという思いが、頭をよぎることがある。
それでも、母の期待に応えるために生きるのではなく、自分が納得できる人生を歩もうと決めた。結婚も出産も、仕事も、外見も、誰が何と言おうとすべて私自身が決めることだ。
母と距離を置くことで、私は少しずつ自分の人生を肯定できるようになった。私自身も大人になり、母との程よい距離感を見つけたことで、少しずつだが自然なコミュニケーションを取れるようになってきた。今は、この外見を含めた私という人間を受け入れてくれるパートナーや友人に恵まれて、穏やかに暮らしている。
そんな今でも「子どもがほしい」と思えないのは、幼い頃から抱えてきた自分自身への複雑な気持ちに、きちんと折り合いをつけることができていないからかもしれない。
親と子の価値観が合わないのは、決して悪いことではない。どんな親子にも起こりうる、当然のことだ。時には距離を置くことも、自分らしく生きるための大切な選択肢だと思う。
もしあなたが今、親子の関係に苦しんでいて、物理的に距離を置くことが難しいと感じているなら、まずはほんの少しだけ、自分に目を向けてみてほしい。相手を変えることは難しいけれど、自分自身の受け止め方や、反応のしかたを変えることはできる。たとえば、言われたことを真に受けすぎず、『これは相手の意見だ』と流してみる。そっと部屋を出て、落ち着くまでは同じ空間にいないようにする。あるいは、信頼できる友人や相談窓口に話を聞いてもらうだけでも、心が少し楽になるかもしれない。
すぐには変わらなくても、そして完全に解決しなくても、それで十分だと思う。あなた自身を、あなたの気持ちを大切にすることを、まずは優先してほしい。