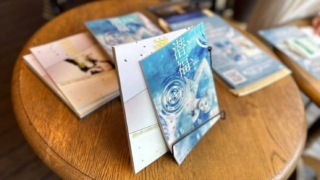前回は、持病のある私とコロナ禍での学童という仕事について書きました。
今回は、コロナ禍によって統合失調症を持つ私がどのような変化をたどったか、記していきたいと思います。
そもそも、新生活を機に統合失調症の服薬を中断していたことから、コロナ禍より前から症状は出ていたように思いますが、今回はコロナ禍を軸に体調の変化を記していきます。
次第に体調が悪化
2020年4月、東京を含む7つの都市に第一次緊急事態宣言が発令されました。
私の住んでいた東京都内の小学校は全て閉鎖されました。
一方で、働く保護者の方の「子どもの預け先がないと働きにいけない」という要望で、都内では学童が日中の預け先となっていました。通勤もままならず自宅での業務を余儀なくされた人も多かったですし、世の中働かないと生きていけないですから、保護者の要望に関してはもっともだと思います。
初めてのことで、学童内もいつもピリピリした状態の中、感染対策や子どもの怪我やケンカにも注意を払わねばなりません。
また、私個人の側面でも、人間関係のいざこざに巻き込まれ、かなり不安やストレスを抱えながら仕事をしていました。
そんな状況が続き、徐々に幻聴や妄想に支配されるようになりました。
頭の中で友人・知人・家族に加えて有名人などの声が頭の中で交錯し、その幻聴の指示に従い行動をしていたり、誇大妄想の世界が本物だと信じて疑わず周りを困らせたりしました。
特に、大学時代に漫画家を目指していた私は、その当時の記憶が蘇り、幻聴に言われるがまま漫画を描き始めました。
当時の自分の中では、幻聴や妄想、世の中の出来事なども含めて、全てが整合性がついているように感じていました。
そして、その幻聴や誇大妄想が現実と信じて疑いませんでした。だから幻聴の指示に従ってしまったのでしょう。
最終的には幻聴以外の声が聞こえなくなり、誇大妄想の世界が現実と信じて疑わない状態に陥り「働いている場合ではない。この幻聴のいう通りに行動せねば漫画家にはなれないのだ。」と、最終的には学童への出勤ができなくなりました。
かなり支離滅裂な内容なのですが、当時の私にとってこれらが全て現実のように感じたのです。
医療保護入院
幻聴や妄想に支配され、仕事もできなくなり、様子がおかしいと思った夫が、運良く大きな精神科の病院へ入院できるよう手筈を整えてくれました。
すでに幻聴や妄想に支配されていた状態でしたので、任意入院ではなく医療保護入院(本人の意思に関係なく治療が必要と診断されて入院すること)という扱いになりました。
入院してから、統合失調症の服薬を再開し、徐々に妄想状態からぬけ出すことができました。
入院して2週間が経った頃には「ああ、私は再発してしまったのだ」と確信していて、誇大妄想の中で生きていた私には、なんとも現実が空虚なものに感じた覚えがあります。
入院生活は約1ヶ月で終わりをつげ、退院することができました。
その後、学童に何度も復帰を試みましたが、統合失調症の陰性症状もひどく、申し訳なさや不甲斐なさから、最終的には退職を選択。
入院中の医師からは「同じような仕事はできるだろうが、職場には戻らない方がいい」と言われていた中での復帰でしたので、どのタイミングで復帰していても退職していたかもしれません。
私にとっても周囲にとっても、あの時はあれが精一杯だった
コロナ禍、特に第一次緊急事態宣言では、皆「今」を乗り越えるのに必死だったのではないか思います。
私も、凄まじい情報の速さやその量に圧倒され、いっぱいいっぱいだった最中、いつしか統合失調症再発という波に飲まれました。
それほど、私たち人間に、かなりの負担をかけた出来事でした。
私は、この時期に起こった全ての出来事を「悪」として片付けたいのではなく「あの時はあれが精一杯だった、皆頑張った」と思いたいのです。
コロナ禍が与えた影響は、計り知れないし、もしかしたら「悪い」ものだったかもしれません。
でも、あの時我々は一生懸命、子どもや家族、自分たちの「命」を守ろうとしていました。
私はコロナ禍により、統合失調症を再発しましたが、おかげさまで現在は安定して平穏な日々を過ごせています。つらい経験でしたが、今は自分の中で折り合いをつけようとしているところです。
多くの人がこのパンデミックで様々な苦しい経験をしたと思います。状況が状況で仕方がなかったと思うことには、何らかの形で折り合いをつけつつ、「みんなそれぞれに頑張ったよね」と自分自身を認めることができたらと願うところです。
あのコロナ禍の折に、社会を支えてくださった全ての皆さまに感謝いたします。