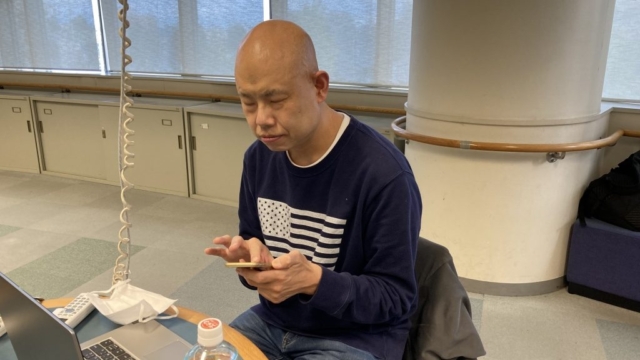頸椎を損傷し、車椅子での生活を始めて十数年になる豆塚エリさん。壮絶な経験を経て、現在は別府でひとり暮らしをしている。
そんな彼女に、身体障害者の日常生活の中でも、とりわけ工夫や配慮が必要とされる「お風呂事情」について聞いてみた。話を聞くうちに見えてきたのは、ただの苦労話ではなく、「社会が少しずつ変わってきた」という手応えだった。
※サムネイル写真は2019年、友人が撮影したもの。
高床式の風呂場で、ひとりでも安心して入浴を

日常生活でのお風呂について、「基本的には全部ひとりでできるように環境を整えています」と豆塚さんは語る。
豆塚さんの身体は、胸から下が完全に麻痺しており、感覚も運動機能もない。そのため、自宅の風呂場はすべて自力で使えるように工夫が施されている。
たとえば、風呂場の床を高床式にリフォームし、車椅子の高さに合わせて畳一枚分ほどのしっかりした台をオーダーメイドで設置。車椅子から足を伸ばしてその台に乗り、ずり上がるように移動すれば、そのまま座った姿勢で体を洗える仕組みになっている。
「浴槽に浸かるのは難しいのですが、浴室乾燥機のおかげで冬場の寒さもある程度はしのげています」と話す。障害のために体温調節に難しさを抱える彼女にとっては、欠かせない設備だ。
感覚がないことで、思わぬリスクが潜んでいることもある。以前、給湯器のトラブルでシャワーから熱湯が出ていることに気づくことができず、足に大きな火傷を負ったことがある。以来、感覚のある部分での温度のチェックを欠かさないようにしているそうだ。
指の力が弱くても使いやすい市販品が増えた
指先の力が弱く、物をしっかり握るのが難しい豆塚さんだが、「握りこまなくても使えるグッズが市販でも手に入るようになってきました」と言う。たとえば、両端にループがついた洗体タオルは、手に引っ掛けるだけで使えるため便利だという。
シャンプー類は、意外にも一般的なポンプ式を使用。体が柔らかいため、足を伸ばしたまま上半身を折りたたんで、あごでポンプを押して使用している。最近流行しているシリコン製の頭皮ブラシも愛用しており、「流行したおかげで可愛いデザインが増えて嬉しい」と笑う。
シャワーヘッドも、手元でオンオフができるボタン付きのものを使っており、「ここ数年で、市販品の選択肢が本当に増えた」と実感しているという。かつては作業療法士にループ付きのタオルを手作りしてもらっていたことを思うと、インクルーシブデザインへの意識が社会全体で高まってきたことを嬉しく感じているという。
バリアフリールーム=安心、とは限らないホテル事情
講演活動などで外泊する機会も多い豆塚さんだが、「ホテル選びには毎回苦労します」と語る。
バリアフリールームがあっても、浴槽と手すりがあるだけで、車椅子ユーザーにとって本当に使いやすいかは別問題だという。車椅子の目線は小学生くらいの高さであるため、アメニティやタオルが手の届かない位置にあることも多い。また、床が絨毯だと車椅子を漕ぐのが大変になることもある。
さらに、バリアフリールームはネット予約で検索できないことも多く、「毎回電話で確認しています」と豆塚さん。だがその一方で、事前に伝えることでホテル側が配慮しやすくなり、「最近は『お手伝いできることはありますか?』と声をかけてくれるホテルが増えました」と話す。
意外だったのが、「実は、バリアフリールームでなくても、部屋が広ければ泊まれることもある」ということだ。予約サイトに記載されている「平米数」がその参考になるという。部屋が広ければ、比例して水回りも広いことが多い。
こうした設計は、「誰でも泊まりやすいように」というインクルーシブな思想に基づいていると感じるそうだ。「あえてバリアフリーと謳っていなくても、結果的にバリアが減っている。そういう宿泊施設が増えてきました」。
別府の温泉と、心のバリアフリー
別府に住む豆塚さんだが、残念ながら自身の障害の状態では、一般的な温泉への入浴は難しい。それでも、体が不自由な人にも入浴しやすいよう、介助用のバスチェアや、浴槽の高さの調整等で配慮してくれる施設は増えていると語る。温泉成分による高い浮力が、入浴のサポートになることもあるそうだ。
また、家族風呂を貸し切った際に事情を伝えると、貸切時間を延長してくれるという温かな心づかいも経験したという。
「昔から湯治場としての文化がある別府では、ソフト面でのバリアフリーを感じていましたが、最近は観光地としてのホスピタリティがより高まっていると感じます」
まとめ
豆塚さんのお風呂事情を通して見えてきたのは、障害があっても自分に合った方法で生活を成り立たせるための工夫、そしてそれを支える社会の変化だった。 超高齢社会で体の不自由な人が増えてきたこともあり、市販のグッズが使いやすく進化し、サービス業にも心のバリアフリーが浸透し始めている。今まで多くの人には見えていなかった「バリア」が、より多くの人に認知されるようになってきたことの表れである。誰もが生きやすいインクルーシブな社会は、一歩ずつ近づいてきている。