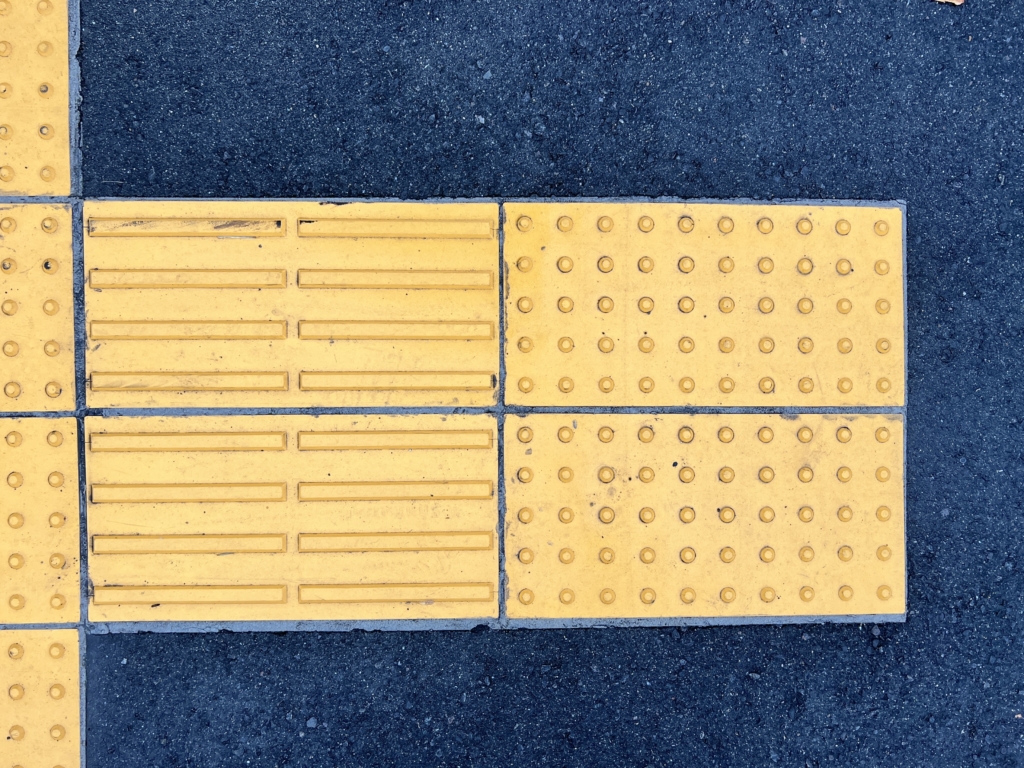
病理医という仕事をしているからでしょうか。たまに、「生きるとは何か」とか、「死ぬとはどういうことか」といった、ほとんど哲学みたいな質問をされることがあります。テーマが大きすぎて私の手には負えないな……と思うのですけれども、問題を小分けにして「病気とは何なのか」くらいまで細かくしますと、なんとかお答えできるようになります。
私が考えますに、病気とは、「昨日までの自分が保てなくなる状態」です。お腹が痛くてご飯が食べられないとか、熱があってだるくて外出できないといったように、「症状によって、昨日まではできていたことができなくなる」と、いかにも病気だなという感じがします。
それでは、「血圧が異様に高い」はどうでしょうか。血圧が高い状態が続くと、血管に少しずつダメージが加わって、いずれは血流を元のように保てなくなります。ですから高血圧はたとえ無症状であったとしても病気とみなして対処したほうがよいです。
症状がなくても病気ということがあり得るのですね。
痛ければ病気? 苦しくなければ健康?
逆のパターンもあります。極端な例ですが、サウナに入っているときは皆さんわりと「ガマン」をされますよね。ウーッと唸って汗をかいて、なんだか苦しそうに見えます。でも、これはもちろん病気ではないですよね。症状があっても病気ではないこともあるわけです。
病気の定義には、痛み、苦しみ、具合の悪さは含まなくてよいのです。
ただし、痛み、苦しみというのは、病名が付こうが付かなかろうが、それ自体がケアされる対象です。病(やまい)という言葉は、つらさ全般に対して与えられ、それが病気かどうかにかかわらず、手当てされてしかるべき状態です。病気とは定義される「もの」ですが、病(やまい)とは人びとがそれぞれ体験する「こと」であり、医療者はその両方に心を配るべきかと思います。ちょっと話がそれました。閑話休題。
因果のあわいに浮かび上がる病気
病気には何かしらの原因があるものだ、と考える方はたくさんいらっしゃいます。「原因が何か悪さをしている」とか、「原因を取り除けば治る」というように。
しかし私は、病気を考えるにあたっては、必ずしも原因を絞り込まなくてもいいと思います。
もちろん、原因がわかりやすい病気はあります。たとえば、食あたり。生ガキを食べたあとに、数日間下痢で苦しんだ場合、原因はノロウイルスだ、などと言いますよね。
でも、原因が特定できる病気というのは、じつはまれです。ほとんどの病気は、複数の素地や要素がフクザツにからみあっており、因果の矢印をうまく辿ることができません。
たとえば、がんという病気では、がん細胞が体の中で増殖します。ならばがんの原因はがん細胞ではないか、と思われるかもしれませんが、それだけではありません。人体の中には免疫機構が存在し、ひとたびがん細胞が出現しても、大抵は免疫がそれらを抑え込んでくれます。しかし免疫とがん細胞の相性によっては、がん細胞が免疫をすり抜けてひそかに増殖を続け、がんの発症に至ります。この場合、がん発症の原因は、がん細胞だけでなく、免疫の側にもあると考えたほうがよいでしょう。
例え話をします。サッカーでは、攻撃側にも防御側にも選手がいますので、やみくもにシュートをしてもゴールには入りません。ディフェンダーやゴールキーパーに防がれますし、味方の選手にあたって跳ね返ってしまうこともあります。フォーメーション、ボールの流れ、選手の体調など、案・因・運・縁がいろいろと噛み合ったときに初めて得点や失点に繋がります。フォワードのキックのうまさとかキーパーのミスだけでゴールが生まれるわけではないですよね。
病気もこれと似ています。攻撃側と防御側が交錯する狭間で生じる均衡の崩れが病気であり、何が原因かを特定することは思った以上に難しいのです。
難病だけが原因不明なわけではない
がん、感染症、膠原病、変性疾患など多くの病気において、病気を促進するファクターと病気を抑え込むファクターが複数入り乱れて、複雑系を形成します。
先ほど、食あたりは因果がわかりやすいなどと書きましたけれど、あれも本当は不正確です。同じ日に同じ食事を食べても下痢を起こさない人もいます。腸内の常在菌のはたらきや免疫の様子が、患者が症状をきたすかどうかに関わるためです。ノロウイルスは原因のひとつではあるでしょうが、原因のすべてではないですし、ノロウイルス以外のウイルスが悪さをしているかもしれません。
でも、現実にはそんなことを言っていると治療が進みませんので、医療現場では病気を単純な因果モデルに近似します。たとえば、細菌感染症においては、細菌だけでなくさまざまな要因が絡んでいることを重々承知の上で、細菌を「原因とみなして」、抗生剤治療を行います。単純化されたモデルの中で仮固定した原因をターゲットに治療をするということです。実際にこれで多くの病気を制御することができます。ただ、所詮は近似に過ぎないので、さまざまな要素の影響によって、治療がうまくいかないこともあります。
「難病」と呼ばれる病気は、しばしば「原因不明」と言われます。でも、あらゆる病気は厳密に言えばすべて原因不明です。単純な因果モデルに近似することが難しい病気を難病と呼ぶ方がより適切でしょう。遺伝子の変異、免疫のバランスの変化、複数のサイトカイン、複数の異常タンパク質などが複雑にからみあって、原因を一つに決められないために、治療のターゲットが確定できないものがいわゆる難病なのです。
複雑系への対処と、これからの医療
原因が確定できず、近似すらも難しい病気の治療はできないのでしょうか?
そうでもありません。医学は少しずつ、複雑系に対応しはじめています。たとえば、がん医療においては、ちょっと前までは分子標的薬と言って「原因を特定してそこをピンポイントで叩く薬」が花盛りでしたが、今はそれに加えて、原因にかかわらず結果を叩く、免疫チェックポイント阻害剤という新たな薬が導入され始めています。さらに、AI(人工知能)の発達によって、人間が理解しきれないくらい複雑な因果の曼荼羅に介入する、新たな創薬の可能性も模索されています。
若いころの私は、さまざまな難病について、いずれ原因が解明されるだろうと信じていました。これは裏を返せば、原因がわからなければ治療はできないというあきらめにもつながる考え方でした。しかし、今は、原因はわからなくても、治療をあきらめなくていいと思えるようになりました。私の中の「原因至上主義」を、医学の進歩が追い抜いていきます。いずれは、原因も、病名すらわからなくても、病気が治せるようになるのかもしれません。私は病理医なので、病気の原因を追求していきたいという気持ちは変わらないのですが、患者にとってまず大事なことは、病気という複雑な「もの」ではなく、病に苦しんでいる「こと」を解決することなのかもしれない、と思っています。






